 › 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 1469年
› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 1469年2015年01月20日
1469年 能阿弥の『花鳥図屏風』完成
トップ > サイトマップ >
 1469(文明元)年の出来事
1469(文明元)年の出来事

1469年 能阿弥(のうあみ)の花鳥図屏風(かちょうずびょうぶ)完成
能阿弥(のうあみ)
室町時代の水墨画家、茶人、連歌師、鑑定家、表具師
生誕 応永4年(1397年)
死没 文明3年(1471年)
元は越前朝倉氏の家臣だったが、室町将軍・足利義教、義政に同朋衆として仕える。
※同朋衆(どうぼうしゅう)とは将軍の近くで雑務や芸能にあたった人々のこと
花鳥図屏風(かちょうずびょうぶ)
能阿弥の代表作。重要文化財。
⇒四季花鳥図屏風 四曲一双(出光美術館)
 1469(文明元)年の出来事
1469(文明元)年の出来事
1469年 能阿弥(のうあみ)の花鳥図屏風(かちょうずびょうぶ)完成
能阿弥(のうあみ)
室町時代の水墨画家、茶人、連歌師、鑑定家、表具師
生誕 応永4年(1397年)
死没 文明3年(1471年)
元は越前朝倉氏の家臣だったが、室町将軍・足利義教、義政に同朋衆として仕える。
※同朋衆(どうぼうしゅう)とは将軍の近くで雑務や芸能にあたった人々のこと
花鳥図屏風(かちょうずびょうぶ)
能阿弥の代表作。重要文化財。
⇒四季花鳥図屏風 四曲一双(出光美術館)
2015年01月19日
1469年 醍醐寺で農民滅亡を祈る読経敢行
トップ > サイトマップ >
 1469(文明元)年の出来事
1469(文明元)年の出来事

1469年 醍醐寺(だいごじ)で農民滅亡を祈る読経敢行
貞観16年(874年)、聖宝により創建。
豊臣秀吉による『醍醐の花見』の行われた地として有名。
文明元年(1469年)、農民たちが年貢の半減を要求して一揆を起こし、醍醐寺の領地を占拠。僧たちは武装して立ち向かうが鎮圧に失敗。
武力でだめなら仏の力を頼るしかないと、農民たちの滅亡を祈る読経を敢行。すると半年後に一揆を起こした農民たちが次々と疫病にかかり死亡。
醍醐寺(だいごじ)
京都府京都市伏見区醍醐東大路町22
 1469(文明元)年の出来事
1469(文明元)年の出来事
1469年 醍醐寺(だいごじ)で農民滅亡を祈る読経敢行
貞観16年(874年)、聖宝により創建。
豊臣秀吉による『醍醐の花見』の行われた地として有名。
文明元年(1469年)、農民たちが年貢の半減を要求して一揆を起こし、醍醐寺の領地を占拠。僧たちは武装して立ち向かうが鎮圧に失敗。
武力でだめなら仏の力を頼るしかないと、農民たちの滅亡を祈る読経を敢行。すると半年後に一揆を起こした農民たちが次々と疫病にかかり死亡。
醍醐寺(だいごじ)
京都府京都市伏見区醍醐東大路町22
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】醍醐寺の歴史と文化財 [ 永村真 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5010%2f9784585225010.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5010%2f9784585225010.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】醍醐寺の歴史と文化財 [ 永村真 ] |
2015年01月16日
1469年 応仁の乱が九州地方に拡大
トップ > サイトマップ >
 1469(文明元)年の出来事
1469(文明元)年の出来事

1469年 応仁の乱が九州地方に拡大
九州北部から中国地方西部を支配していた西軍の有力大名・大内政弘(おおうちまさひろ)。
⇒【応仁の乱】1467年8月、西軍・大内政弘が周防から京に到着
⇒【応仁の乱】1477年11月11日、西軍の武将たちが領地に帰還し引き分けに
大内政弘が京に出陣しているすきに、東軍の細川勝元の誘いに乗った九州の大友親繁、少弐政質らが大内政弘の叔父・教幸を擁して西軍の大内領を攻撃。
京で勃発した応仁の乱はついに九州まで拡大。
大内政弘(おおうちまさひろ)
室町時代の守護大名。大内氏第14代当主。
生誕 文安3年8月27日(1446年9月18日)
死没 明応4年9月18日(1495年10月6日)
応仁の乱では西軍・山名宗全方に属し、応仁元年(1467年)に上洛、その後10年間にわたり畿内各地を転戦する。
文明元年(1469年)、東軍方の大友親繁、少弐政質ら大内政弘の不在を突いて攻撃。翌1470年、大内政弘の叔父・教幸が赤間関(現・下関市)で謀反を起こす。重臣・陶弘護らの活躍で乱を鎮圧。叔父・教幸は自害。
応仁の乱収束後、山口に帰国。
文明10年(1478年)、九州に出陣して少弐氏を破り豊前・筑前を確保する。安芸、石見の豪族や国人らを臣従させ、北九州や瀬戸内海の海賊衆を平定するなど西国の支配権確立に力を傾ける。
京都を焦土と化した応仁・文明の乱は戦国時代の幕開けだったのか? 日野富子を元凶とする『応仁記』がもたらした定説は、近年見直されつつある。幕府内部や関東の政情不安にも光を当て、新たな応仁・文明の乱を描く。
 1469(文明元)年の出来事
1469(文明元)年の出来事
1469年 応仁の乱が九州地方に拡大
九州北部から中国地方西部を支配していた西軍の有力大名・大内政弘(おおうちまさひろ)。
⇒【応仁の乱】1467年8月、西軍・大内政弘が周防から京に到着
⇒【応仁の乱】1477年11月11日、西軍の武将たちが領地に帰還し引き分けに
大内政弘が京に出陣しているすきに、東軍の細川勝元の誘いに乗った九州の大友親繁、少弐政質らが大内政弘の叔父・教幸を擁して西軍の大内領を攻撃。
京で勃発した応仁の乱はついに九州まで拡大。
大内政弘(おおうちまさひろ)
室町時代の守護大名。大内氏第14代当主。
生誕 文安3年8月27日(1446年9月18日)
死没 明応4年9月18日(1495年10月6日)
応仁の乱では西軍・山名宗全方に属し、応仁元年(1467年)に上洛、その後10年間にわたり畿内各地を転戦する。
文明元年(1469年)、東軍方の大友親繁、少弐政質ら大内政弘の不在を突いて攻撃。翌1470年、大内政弘の叔父・教幸が赤間関(現・下関市)で謀反を起こす。重臣・陶弘護らの活躍で乱を鎮圧。叔父・教幸は自害。
応仁の乱収束後、山口に帰国。
文明10年(1478年)、九州に出陣して少弐氏を破り豊前・筑前を確保する。安芸、石見の豪族や国人らを臣従させ、北九州や瀬戸内海の海賊衆を平定するなど西国の支配権確立に力を傾ける。
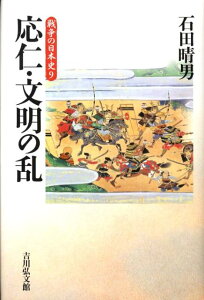 【楽天ブックスならいつでも送料無料】戦争の日本史(9) 応仁・文明の乱 |
京都を焦土と化した応仁・文明の乱は戦国時代の幕開けだったのか? 日野富子を元凶とする『応仁記』がもたらした定説は、近年見直されつつある。幕府内部や関東の政情不安にも光を当て、新たな応仁・文明の乱を描く。
2015年01月15日
1469年 雪舟が明(中国)から帰国
トップ > サイトマップ >
 1469(文明元)年の出来事
1469(文明元)年の出来事
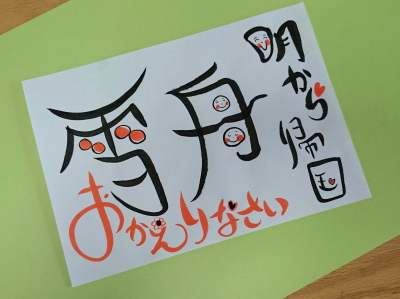
1469年 雪舟(せっしゅう)が明(中国)から帰国
2年前の1467年 雪舟が明に留学。
雪舟(せっしゅう)
室町時代の水墨画家、禅僧
生誕 応永27年(1420年)
死没 永正3年8月8日(1506年) 諸説あり
京都の相国寺で修行した後、周防の守護大名・大内氏の庇護を受け、画室雲谷庵(山口県山口市)を構える。
応仁元年(1467年)、遣明船で明へ渡航。2年間にわたって本格的な水墨画を学ぶ。
文明元年(1469年)に帰国し。周防のほか豊後や石見で創作活動を行う。
 1469(文明元)年の出来事
1469(文明元)年の出来事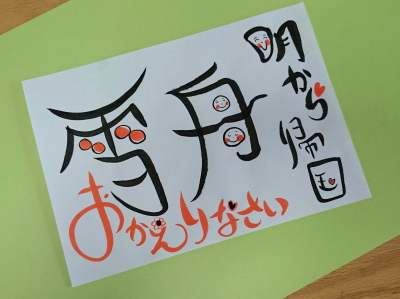
1469年 雪舟(せっしゅう)が明(中国)から帰国
2年前の1467年 雪舟が明に留学。
雪舟(せっしゅう)
室町時代の水墨画家、禅僧
生誕 応永27年(1420年)
死没 永正3年8月8日(1506年) 諸説あり
京都の相国寺で修行した後、周防の守護大名・大内氏の庇護を受け、画室雲谷庵(山口県山口市)を構える。
応仁元年(1467年)、遣明船で明へ渡航。2年間にわたって本格的な水墨画を学ぶ。
文明元年(1469年)に帰国し。周防のほか豊後や石見で創作活動を行う。
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】もっと知りたい雪舟 [ 島尾新 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8610%2f9784808708610.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8610%2f9784808708610.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】もっと知りたい雪舟 [ 島尾新 ] |
2015年01月14日
1469年 古市澄胤が淋汗茶湯を開催
トップ > サイトマップ >
 1469(文明元)年の出来事
1469(文明元)年の出来事

1469年 古市澄胤(ふるいちちょういん)が淋汗茶湯(りんかんちゃのゆ)を開催
古市澄胤(ふるいちちょういん)
戦国時代の僧、武将
生誕 享徳元年(1452年)
死没 永正5年7月26日(1508年8月22日)
大和国古市郷(奈良県奈良市)の領主であり、興福寺の僧。
淋汗茶湯(りんかんちゃのゆ)
入浴(淋汗)した後に衣服に着替えて、茶と酒を楽しむ催事。
風呂の他、庭に松竹を植えて、山を作り滝を流し、周囲には花が飾られ、唐絵や香炉、食籠(じきろう)などが置かれ、飾り付けられた作り物を見ながら茶や酒を楽しむ会。
興福寺の僧や、古市郷の領民など、身分を問わず多くの人たちが淋汗茶湯を楽しんだ。
文化と宗教(鎌倉・室町期の箱根権現別当/ 茶道史における「淋汗茶湯」の位置付け ほか)
 1469(文明元)年の出来事
1469(文明元)年の出来事
1469年 古市澄胤(ふるいちちょういん)が淋汗茶湯(りんかんちゃのゆ)を開催
古市澄胤(ふるいちちょういん)
戦国時代の僧、武将
生誕 享徳元年(1452年)
死没 永正5年7月26日(1508年8月22日)
大和国古市郷(奈良県奈良市)の領主であり、興福寺の僧。
淋汗茶湯(りんかんちゃのゆ)
入浴(淋汗)した後に衣服に着替えて、茶と酒を楽しむ催事。
風呂の他、庭に松竹を植えて、山を作り滝を流し、周囲には花が飾られ、唐絵や香炉、食籠(じきろう)などが置かれ、飾り付けられた作り物を見ながら茶や酒を楽しむ会。
興福寺の僧や、古市郷の領民など、身分を問わず多くの人たちが淋汗茶湯を楽しんだ。
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】戦国織豊期の社会と儀礼 [ 二木謙一 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f6420%2f64202850.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f6420%2f64202850.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】戦国織豊期の社会と儀礼 [ 二木謙一 ] |
文化と宗教(鎌倉・室町期の箱根権現別当/ 茶道史における「淋汗茶湯」の位置付け ほか)
2015年01月13日
1469年 斎藤妙椿が略奪した郡上郡を東常縁に返還
トップ > サイトマップ >
 1469(文明元)年の出来事
1469(文明元)年の出来事

1469年 斎藤妙椿(さいとうみょうちん)が略奪した郡上郡を東常縁(ひがしつねより)に返還
斎藤妙椿(さいとうみょうちん)
室町時代から戦国時代の武将、僧侶
生誕 応永18年(1411年)
死没 文明12年2月21日(1480年4月1日)
斎藤妙椿は応仁の乱で美濃守護・土岐成頼と共に山名宗全の西軍に属す。
上洛中の土岐成頼に代わり、東軍に属した富島氏・長江氏、近江より来援に来た京極氏の軍勢と戦い、応仁2年(1468年)10月までに美濃国内を平定。
応仁の乱勃発時、美濃篠脇城主・東常縁は下総に居り、斎藤妙椿が美濃を攻撃、占領。
東常縁(ひがしつねより)
室町時代中期から戦国時代初期の武将、歌人
生誕 応永8年(1401年)?
死没 文明16年3月16日(1484年4月20日)?
康正元年(1455年)、関東で享徳の乱(きょうとくのらん)が発生。東常縁は室町幕府8代将軍・足利義政の命により関東を転戦。
関東滞在中に応仁の乱が発生し、所領の美濃郡上を斎藤妙椿に奪われた。
東常縁が所領を奪われた悲しみを和歌に詠んだところ、これが評判となり、和歌に興味をもっていた斎藤妙椿が、東常縁に対して、自らの心情を和歌にして自分に送るように提案。以来、両者の間で和歌のやりとりがなされ、東常縁の和歌に感動した斎藤妙椿が奪った領地を返還。
 1469(文明元)年の出来事
1469(文明元)年の出来事
1469年 斎藤妙椿(さいとうみょうちん)が略奪した郡上郡を東常縁(ひがしつねより)に返還
斎藤妙椿(さいとうみょうちん)
室町時代から戦国時代の武将、僧侶
生誕 応永18年(1411年)
死没 文明12年2月21日(1480年4月1日)
斎藤妙椿は応仁の乱で美濃守護・土岐成頼と共に山名宗全の西軍に属す。
上洛中の土岐成頼に代わり、東軍に属した富島氏・長江氏、近江より来援に来た京極氏の軍勢と戦い、応仁2年(1468年)10月までに美濃国内を平定。
応仁の乱勃発時、美濃篠脇城主・東常縁は下総に居り、斎藤妙椿が美濃を攻撃、占領。
東常縁(ひがしつねより)
室町時代中期から戦国時代初期の武将、歌人
生誕 応永8年(1401年)?
死没 文明16年3月16日(1484年4月20日)?
康正元年(1455年)、関東で享徳の乱(きょうとくのらん)が発生。東常縁は室町幕府8代将軍・足利義政の命により関東を転戦。
関東滞在中に応仁の乱が発生し、所領の美濃郡上を斎藤妙椿に奪われた。
東常縁が所領を奪われた悲しみを和歌に詠んだところ、これが評判となり、和歌に興味をもっていた斎藤妙椿が、東常縁に対して、自らの心情を和歌にして自分に送るように提案。以来、両者の間で和歌のやりとりがなされ、東常縁の和歌に感動した斎藤妙椿が奪った領地を返還。
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】濃飛歴史人物伝 [ 濃飛の歴史を語る会 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1465%2f9784877971465.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1465%2f9784877971465.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】濃飛歴史人物伝 [ 濃飛の歴史を語る会 ] |
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】東常縁 [ 井上宗雄 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2fnoimage_01.gif%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2fnoimage_01.gif%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】東常縁 [ 井上宗雄 ] |

