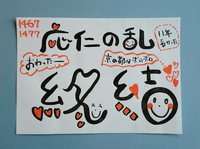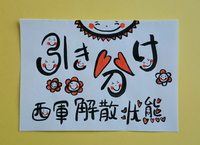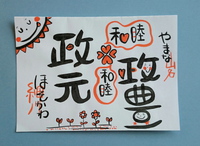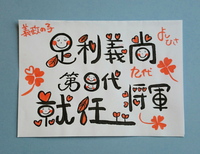2014年11月06日
【応仁の乱の背景】管領・畠山家の後継問題
トップ > サイトマップ >
前ページのつづき
 【応仁の乱の背景】管領・斯波氏の後継問題
【応仁の乱の背景】管領・斯波氏の後継問題
畠山(はたけやま)氏
三管領の一族。
管領・・・将軍に次ぐ地位で、将軍を補佐し、将軍の命令を直接受けて下に伝達する。この人たちは足利一門の有力守護である細川・斯波・畠山の三氏から選任され就任した。 この三つの一族を三管領(さんかんれい)という。
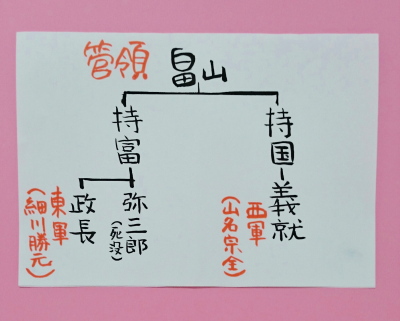
当主・畠山持国(はたけやまもちくに)は、河内(大阪府)、紀伊(和歌山県)、越中(富山県)三国の守護職をもち、細川勝元と互いに管領の要職について幕府の体制を固めた。
しかし、彼には初め実子がなく、弟・持富(もちとみ)を養子にしたの。ところが、のちに側室に義就(よしなり)が生まれたので家督を譲り、持富を廃嫡したの。これって、将軍・義政のところと一緒だよね(⇒足利将軍家の後継問題)。だから畠山家もお家騒動が起こるの。
持国は我が子・義就に家督を譲ったんだけど、重臣たちは納得しなかったの。それでごたごたが起きるんだけど、重臣のなかには持国の処理に不満をもち、持富の子・弥三郎(死没)やその弟・政長を家督にしようと計画し、細川勝元の援助を受けて、持国を隠居させるとともに、義就を廃嫡し、享徳3年(1454年)8月、政長を畠山家の当主としたの。そして寛正5年(1464年)11月、細川勝元の後任の管領に就任したの。
ここで収まればよかったんだけど、廃嫡、追放された義就がだまっていないんだよね。
追放された義就は山名宗全を頼って再び上洛し、文正元年(1466年)12月、赦されて将軍・義政に目通りするんだけど・・・
ここから、いよいよ応仁の乱の幕開け。
つづく
⇒【応仁の乱のきっかけ】1466年12月、畠山義就が河内から出陣
前ページのつづき
 【応仁の乱の背景】管領・斯波氏の後継問題
【応仁の乱の背景】管領・斯波氏の後継問題畠山(はたけやま)氏
三管領の一族。
管領・・・将軍に次ぐ地位で、将軍を補佐し、将軍の命令を直接受けて下に伝達する。この人たちは足利一門の有力守護である細川・斯波・畠山の三氏から選任され就任した。 この三つの一族を三管領(さんかんれい)という。
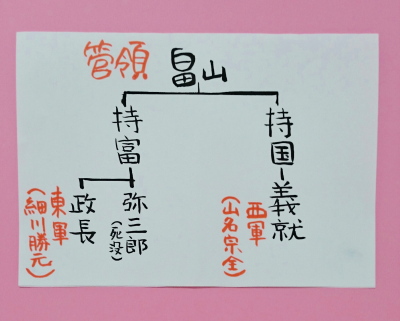
当主・畠山持国(はたけやまもちくに)は、河内(大阪府)、紀伊(和歌山県)、越中(富山県)三国の守護職をもち、細川勝元と互いに管領の要職について幕府の体制を固めた。
しかし、彼には初め実子がなく、弟・持富(もちとみ)を養子にしたの。ところが、のちに側室に義就(よしなり)が生まれたので家督を譲り、持富を廃嫡したの。これって、将軍・義政のところと一緒だよね(⇒足利将軍家の後継問題)。だから畠山家もお家騒動が起こるの。
持国は我が子・義就に家督を譲ったんだけど、重臣たちは納得しなかったの。それでごたごたが起きるんだけど、重臣のなかには持国の処理に不満をもち、持富の子・弥三郎(死没)やその弟・政長を家督にしようと計画し、細川勝元の援助を受けて、持国を隠居させるとともに、義就を廃嫡し、享徳3年(1454年)8月、政長を畠山家の当主としたの。そして寛正5年(1464年)11月、細川勝元の後任の管領に就任したの。
ここで収まればよかったんだけど、廃嫡、追放された義就がだまっていないんだよね。
追放された義就は山名宗全を頼って再び上洛し、文正元年(1466年)12月、赦されて将軍・義政に目通りするんだけど・・・
ここから、いよいよ応仁の乱の幕開け。
つづく
⇒【応仁の乱のきっかけ】1466年12月、畠山義就が河内から出陣
Posted by 夢子 at 11:40
│応仁の乱